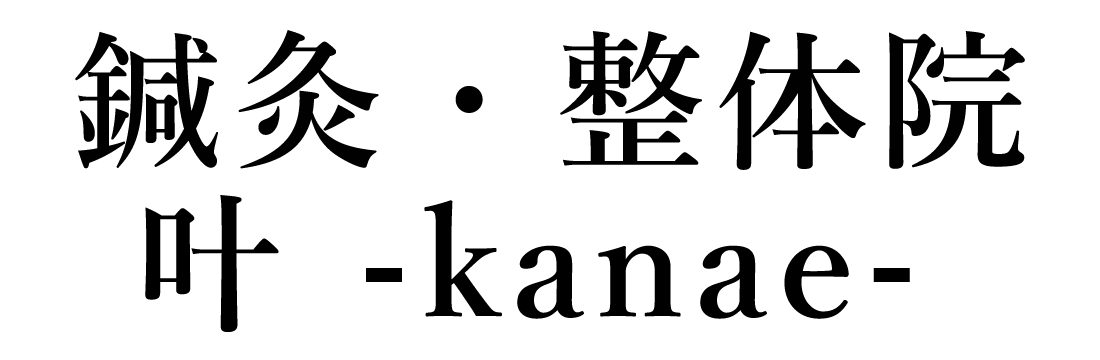今回は「喘息とメンタルヘルス」の関係性についてお話しします。
まず、今回は喘息を「呼吸器疾患」として広義に説明します。
息苦しさには、いくつかの原因があります。
息の吸いづらさ。
息の吐きづらさです。
いわゆる肺活量の話ですね。
息が吸いづらい場合、首肩こり、肋骨や背中の筋肉の硬さ。
または肺に何らかの問題が考えられます。
レントゲンを撮ると、肺が白く写ることがあります。
過去にコロナにかかっていたり長年の喫煙歴、粉塵を吸ってしまうような仕事など。
そういうダメージの蓄積で肺組織が硬くなっており癌で水が溜まっていた場合に画像所見で明らかになります。
この難しい話を簡単に例えると、ふーっとかるい感じで膨らむ風船のゴムがめちゃくちゃ硬くなってしまっていて膨らまない状態です。
酸素を受け入れる肺が硬ければ当然、それを受け入れる柔軟性も容量も乏しいですよね。
肺は横隔膜の収縮によって動くのですが、肋骨が広がったり縮んだりして受け入れる酸素の量が変化します。
肋骨や背中の筋が凝っていると肋骨が動かないので肺は膨らみません。
この点、病院では検査に含まれないので盲点になることがあり息苦しさの原因は気持ちの問題だと診断されることも珍しくありません。
一方、吸えるけど吐きづらい場合は肺に問題がありません。
気管支と言って、口から肺に繋がる首と胸あたりの管に問題が考えられます。
その管が太ければ酸素がとおりやすいし、細ければとおりにくいです。
口を大きく開けて息を吐くのと、口をすぼめて息を吐くのとでは全然違いますよね?
酸素の通り道である気管支は、副交感神経で支配されています。
これはリラックス時に働くのですが、睡眠時に気管支は狭くなります。
夜に咳が出るのはそのせいで、苦しさは気管支を広くする交感神経の働きに切り替わる起床時まで続きます。
かるい運動をすると気管支が広がり心拍数も安定するので、おすすめです。
それとは別にストレスや心配性の性格によって、動悸が胸苦しさに関係します。
心拍数が100や120くらいいくと、冷や汗や不安感も強くなるはずです。
これは死には直結しないもののパニック障害や適応障害の恐れがあるし、うつ病でなくてもうつ状態にもなり得ます。
心と体は表立体ですので、鍼やマッサージを当院へ受けに来て下さい。
きっと、今よりも楽になります。